家族あての郵便物の受取拒否は可能?手順や書き方についても解説
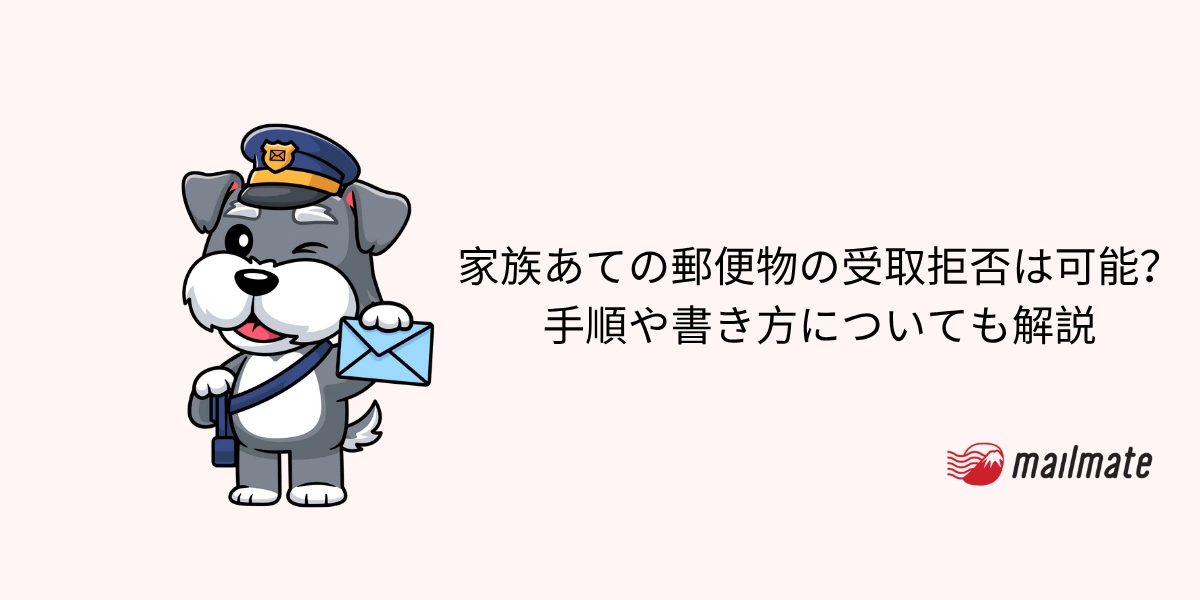
家族宛の郵便物が届いたとき、「これは受け取りたくないな……」と思うことはありますよね。架空請求や不要な広告、元配偶者宛の郵便など、状況はさまざまです。しかし、家族が勝手に受領印を押して受け取ってしまった場合、郵便物やゆうパックの受け取り拒否は少し複雑です。正しい知識がないと、どう対応していいか迷ってしまうこともあります。
この記事では、家族宛の郵便物を受け取り拒否できるケースや手続き方法、拒否できない郵便物の例、さらに拒否後の郵便物の扱いについて、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。これを読めば、不要な郵便や荷物の処理がスムーズになり、トラブルを避けつつ安全に管理できるようになるでしょう。
クラウド郵便のMailMateがお客様の郵便物を受け取り代行・スキャン・PDF化いたします。自宅宛の郵便物をパソコンやスマホ上で管理🛡
家族あての郵便の受け取り拒否はできる?【架空請求など】
![Can I refuse to receive mail addressed to my family? [Fictious billing, etc.]](http://images.ctfassets.net/rrofptqvevic/6yAN22RMou1Z5HWxzzUlOp/aad3794a3ea8b648a9efdf0f8f41ec93/600_300_MailMate_VN__31_.webp)
家族あてに届いた郵便物でも、差出人が不明だったり、明らかに架空請求などの不審な内容であれば、基本的に「受け取り拒否」が可能です。ただし、郵便物の宛名が明確に「本人宛」になっている場合、原則としてその本人以外が勝手に拒否手続きを行うことはできません。
たとえば「山田太郎様」と個人名で届いた郵便物を家族が勝手に拒否することは、郵便局では認められないケースが多いです。そのため、不審郵便を避けたい場合は「本人に確認して拒否の意思を書いてもらう」か、「本人の署名をもって受け取り拒否の意思表示をする」必要があります。
ただし、明らかに詐欺まがいの内容や脅迫的な文面がある場合は、開封せずに警察や消費生活センターへ相談するのが安全です。
離婚した家族の郵便物受け取り拒否はできる?
離婚後に元配偶者あての郵便物が届くケースも少なくありません。この場合、すでに別居しており同居していないなら「受取人不在」として返送して問題ありません。
郵便局では、あて先が現住所に居住していないと判断できる場合、「あて所に尋ねあたりません」として差出人に返送します。そのため、宛先人がすでに転居している場合は、「この住所には居住していない旨」を封筒に明記してポストに投函すればOKです。
一方で、まだ同居している場合は、基本的に本人の同意がなければ拒否できません。勝手に返送するとトラブルになる恐れがあるため、本人に確認したうえで手続きを行いましょう。
詳しくはこちら:離婚後の住所を知られたくない時はどうする?対応策を詳しく解説
家族が死亡している場合、郵便物受け取り拒否はできる?
亡くなった家族あてに届く郵便物は、基本的に遺族であっても受け取れません。郵便局では、死亡の事実が確認できれば「受取人死亡」として差出人に返送する扱いになります。
もし家族が亡くなっているけれど認識されておらず郵便物が届き続ける場合は、郵便局に連絡して受取人が死亡していることを伝えるとよいでしょう。また、クレジットカード会社や公共料金などの連絡は、自動的に発送されている場合も多いため、業者に直接連絡を入れておくと今後の送付を止めてもらえます。
ただし、相続関連の重要書類などは返送してしまうと手続きに支障が出ることもあります。内容を確認し、必要に応じて弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
住んでいない家族の郵便物は受け取り拒否できる?
同じ苗字だからといって、住んでいない家族の郵便物を受け取る義務はありません。宛先人が実際にその住所に住んでいない場合、その旨を明記して返送できます。
たとえば、成人した子どもが独立した後も実家宛にDMや請求書が届くケースでは、受け取らずにそのまま返送して問題ありません。ただし、重要な通知(税金、保険、行政関係など)の場合は、誤って返送しないよう注意が必要です。できれば、受取人本人が差出人に対し、現在の住所に送ってもらうよう連絡するのがよいでしょう。
受け取り拒否を行う際は、「宛名の本人が現住所にいないこと」を明確にすることが大切です。郵便局でも、再三届く郵便物に関しては、転送届の提出を案内してもらえる場合があります。
家族あての郵便物の受け取り拒否をする方法

家族あての郵便物を受け取り拒否する方法は、郵便物の種類によって異なります。基本的な流れは以下のとおりです。
封筒やはがきを開封せずに、「受取拒絶」と明記する。
宛名人本人の署名または印鑑を押す。
そのままポストに投函する、または郵便局の窓口に提出する。
この手続きで、差出人に返送されます。
ただし、受領印が必要な郵便物(書留・簡易書留など)は、受け取り時点で署名してしまうと拒否できなくなるため、次項で説明する手順を確認してください。
受領印が必要な郵便物の場合
書留や簡易書留、特定記録郵便など、受け取り時に受領印(またはサイン)が必要な郵便物は、受け取る前に拒否の意思を伝えることが重要です。
一度受領印を押してしまうと、「受け取り完了」と見なされ、原則として拒否ができなくなります。
もし配達員が来た時点で受け取りたくないと判断したら、開封せずに「受け取り拒否します」と伝えましょう。その場で差出人に返送されます。
なお、本人不在で家族が応対した場合でも、家族の署名では正式な拒否にならないケースがあります。宛名人が後日、郵便局に連絡して手続きを行うようにしましょう。
受け取りに受領印が必要ない郵便物(はがきなど)の場合
はがきや普通郵便のように受領印が不要な郵便物は、ポストに投函された後でも受け取り拒否が可能です。
方法は簡単で、封筒やはがきに「受け取り拒否」と明記し、宛名人の署名または印を押してポストに入れるだけです。切手を貼る必要はなく、郵便局が差出人に無料で返送してくれます。
ただし、開封してしまった場合は拒否が認められません。中身を見た時点で「受け取った」と判断されるため、迷ったときは開けずに拒否するのが鉄則です。
また、DMや勧誘のはがきが頻繁に届くようなら、差出人に「今後の送付を停止してほしい」と連絡するのも効果的です。
関連記事:【見られたくない!】家族に知られず郵便物を受け取る方法まとめ
受け取り拒否ができないものの例

郵便物の中には、法律上や配達の性質上、受け取り拒否ができないものもあります。誤って返送するとトラブルになることもあるため、以下のようなケースには注意しましょう。
特別送達の郵便物
特別送達とは、裁判所などから届く重要な書類(訴状や呼出状など)を送るための郵便です。
これは「法的効力を伴う通知」として扱われるため、受け取りを拒絶することはできません。仮に拒否しても「受け取ったもの」と見なされ、裁判の手続きが進行してしまうおそれがあります。
内容が分からないまま放置するのは危険なので、届いた場合は速やかに開封し、必要なら弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
宅急便コンパクトなど
郵便局ではなくヤマト運輸などの民間配送サービスを利用した荷物(宅急便コンパクトなど)は、郵便物ではないため扱いが異なります。
受け取り拒否自体は可能ですが、返送時の送料をこちらが負担する場合があります。また、発送元の規約によっては、返品手続きが必要になるケースも。
不審な荷物であれば、まずはドライバーに「受け取りを辞退します」と伝え、開封せずに差出人へ返してもらいましょう。
ネコポスなど
ネコポスやクリックポスト、メール便といった郵便物ではないポスト投函型のサービスは、基本的に受領印が不要なため、配達完了後の拒否はできません。
もし身に覚えのない荷物が届いた場合は、ヤマト運輸や郵便局など、配達業者の問い合わせ窓口に連絡し、差出人情報を確認するのが先決です。
中には悪質な「送りつけ商法」のケースもあるため、開封せずに保管し、消費生活センターへ相談するのも有効です。
飛脚メール便など
佐川急便の「飛脚メール便」も同様に、郵便物ではなくポストに直接投函されるため、原則として受け取り拒否はできません。
ただし、差出人が明確なDMなどであれば、封筒に「受け取り拒否・今後送付不要」と明記して返送することで、送付停止につながる場合もあります。
継続的に届く場合は、佐川急便の問い合わせ窓口に相談し、差出人への配達停止措置をお願いしてみるのもおすすめです。
こちらもおすすめ:差出人・受取人の住所を知られたくないときの郵送方法!
郵便物を受け取り拒否したその後はどうなる?

受け取り拒否をした後、その郵送物は、郵便局や配送業者を通じて差出人のもとに返されます。差出人側は封筒に「受取拒否」と明記された状態で返送を受け取るため、基本的には相手に拒否の意思が伝わります。
ただし、差出人が法人や自動送信のシステムを利用している場合、「宛先不明」として処理されることもあります。
また、受け取り拒否した後も同じ差出人から郵便が届く場合は、差出人に直接連絡して荷物を発送しないでほしい旨を伝えるとよいでしょう。
郵便物を受け取り拒否した場合、相手にはバレる?
受け取り拒否をした場合、差出人にはその返還した荷物が届くため、たいていの場合拒否されたことがわかります。
ただし、返送の理由が「受取拒否」とは限らず、「あて所に尋ねあたりません」となっている場合は、単に住所違いと判断されることもあります。
個人間のトラブルで相手に知られたくない場合は、「受取拒否」ではなく「転居済み」「宛名不明」など別の返送理由を選ぶ方法もありますが、虚偽記載をするとその他の郵便物が届かなくなってしまう可能性もあり、おすすめできません。どうしても差出人と関わりたくない場合は、警察や弁護士などに相談して、正しい方法で対応を進めましょう。
郵便物の受け取り拒否に期限はある?
郵便物の受け取り拒否には明確な期限はありませんが、受け取ってから一定期間経過すると対応が難しくなることがあります。
たとえば、ポストに入ってから数週間経っている郵便を今さら返送しても、郵便局側で「配達完了」と扱われているため、返送を受け付けてもらえないことがあります。
受け取り拒否をする場合は、届いてからできるだけ早めにポストへ投函するのがポイントです。目安として、到着後1週間以内が望ましいでしょう。
家族が勝手に郵便物の受け取り拒否をしてしまった場合

もし家族が本人に無断で郵便物を拒否してしまった場合は、まず郵便局や配送業者に連絡して事情を説明しましょう。返送前なら、宛先人の意思確認をもとに再配達へ切り替えられるケースがあります。
しかし、すでに差出人へ返送済みの場合は、送り主に再送をお願いするしかありません。特に公的機関や金融機関などからの重要郵便であれば、誤送扱いでは済まないこともあるため、早めの対応が必要です。
また、頻繁に家族が勝手に対応してしまうようなら、「宛名ごとに本人確認をしてから受け取る」ルールを家庭内で決めておくのが安心です。
郵便局に連絡
郵便物が日本郵便によって届けられた場合は、まず最寄りの郵便局に連絡します。郵便局では、該当の郵便物の状況を確認し、場合によっては差出人へ返送される前に保管しておいてもらえるなどの対応が受けられることもあります。
郵便物が重要なものである場合は、局員に事情を説明し、受け取りたいという意思があったことを伝えると、返送の手続きを止めてもらえる可能性があります。電話で状況を相談するほか、窓口で直接、受け取り希望を伝える方法もあります。
宅配便等の場合は運送業者に連絡
ヤマト運輸や佐川急便などの宅配便で受け取り拒否が行われた場合は、各運送業者に直接連絡します。受け取りを拒絶する際の対応は業者ごとに異なるため、電話で詳細を確認し、再配達や返送の可否、手続きの方法を確認することが重要です。
特にヤマト運輸では、基本的には受領後に荷物を返還することは不可であり、返送したい場合は送り主に連絡する必要があります。佐川急便も、担当営業所への問い合わせが基本です。
返送されてしまった場合は送り主に連絡
受け取り辞退をして荷物が差出人まで返ってしまった場合は、差出人に再送や対応を依頼します。特に重要書類や請求書などの場合、返送後に期限が過ぎるとトラブルにつながることがあります。
差出人に事情を説明し、再送や電子データでの送付など、可能な対応方法を確認しましょう。郵便物や荷物の種類によっては、再発行や再送に手数料がかかる場合もあるため、迅速に連絡することが大切です。
MailMateが郵便物を受け取り代行・スキャン・PDF化。到着通知が即座に届くから重要書類も見逃しません。家族と受取住所を完全に分けられます。
間違えて受け取り拒否をしてしまった場合

封筒を取り違えたり、不審郵便と勘違いして拒否してしまうケースもあります。もし重要な書類を返還してしまった場合は、返還日・追跡番号・郵便局名を控えておくと、再発行依頼時にスムーズです。
再送をお願いする際は、相手に誤解を与えないよう「誤って受け取り拒否をしてしまいました」と正直に伝えるのが大切です。
自分や家族あての郵便物を事前に受け取り拒否できるのか
郵便物を「届く前にお断りしたい」という場合もあるでしょう。しかし、基本的に郵便物は、追跡番号などが判明していても、事前の電話などで受け取りを辞退することはできません。
もちろん、普通郵便やDMなども差出人が郵送した時点で管理対象外となるため、事前拒否は基本的にできません。
同じ差出人からくりかえし郵便が届くのを事前に防止したいという場合は、送ってくる相手に直接伝えてもうその荷物を発送しないでほしいとお願いするとよいでしょう。
ゆうパックなどの荷物は電話で事前に受け取り拒否できる?
結論から言うと、ゆうパックなどの荷物を電話だけで事前に受け取り拒否する方法は、公式には案内されていません。日本郵便の公式サイトやFAQにも、「電話での事前受取拒否」という手続きに関する記載はなく、確実に受け取らないようにする正式な方法は公開されていません。
つまり、配達前に「届く予定の荷物を止めて返送する」というような電話依頼は、原則としてできないと考えるのが安全です。ただし、荷物が配送局に到着した後であれば、郵便局窓口に持参して「受取拒否」の申出をすることは可能です。
また、特定の条件を満たす場合(郵便物が未開封で受領印不要な場合など)は、受け取り後でも返還できることもあります。受け取り拒否を考える場合は、配達前ではなく配達時の手続きが基本になると理解しておくのがよいでしょう。
「郵便物 受け取り拒否 家族」に関するよくある質問

こちらの項目では、郵便物の受取拒否に関するよくある疑問に回答します。
受領印を押してしまった郵便物は受け取り拒否できない?
通常、受領印を押すと郵便物は「受領済み」とみなされ、原則、送り返すことはできません。たとえ中身を確認していなくても、署名・押印した時点で受け取りの契約が成立するためです。ただし例外として、次の条件をすべて満たす場合のみ、ゆうパックなどでも受取辞退が可能です。
企業や病院、集合住宅の管理室など、多人数が出入りする場所で代理的に受領印が押されたもの
受領後遅滞なく受取拒否の申し出があること
開封しておらず封かんに異常がないこと
配達証明・特別送達・代金引換を利用していないこと
これらを満たす場合に限り、郵便局で受取拒否の申出ができます。それ以外の場合は受領後の拒否は認められません。万が一不審な郵便物の場合は開封せずに郵便局や警察・消費生活センターに相談することが推奨されます。
開けてしまった郵便物は受け取り拒否できない?
はい。郵便物を開封した瞬間に「内容を確認した=受け取った」とみなされるため、受け取り辞退はできません。たとえ誤って開けた場合でも、開封済みの郵便物は差出人へそのまま返送できない仕組みになっています。
もし誤配や宛先違いだった場合は、そのまま封を閉じて郵便局へ持参し、「誤配達のようなので返送したい」と相談するのが正しい対応です。勝手に捨ててしまうとトラブルの原因になります。
また、詐欺や迷惑郵便が届いて開けてしまった場合は、証拠保全のために封筒や中身を保管し、消費生活センターや警察への相談をおすすめします。開封後は「拒否」ではなく「相談・対応」のステップへ進むのが安全です。
受け取り拒否したい荷物を家族が受け取ってしまった
家族が代わりに荷物を受け取ってしまった場合、基本的に受領の辞退はできません。ただし、郵便物であれば一定の条件を満たす場合に限り、受け取り後でも拒否が可能です。
その条件は、①郵便物であること、②開封されていないこと、③受領印や受け取りサインが不要なもの(ポスト投函など)であることです。
これらを満たす郵便物であれば、郵便局に持参して返送手続きを依頼できます。一方、宅配便などその他の荷物では状況が異なります。たとえばヤマト運輸では、受け取り後の返送は原則不可で、返送したい場合は送り主に連絡する必要があります。
佐川急便の場合も、公式サイトでは担当営業所への問い合わせを推奨しており、返送可否は荷物や条件によって異なります。家族が誤って受け取った場合でも、無理に処理せず、まずは郵便局や配送業者に状況を説明し、適切な対応方法を確認することが重要です。
家族の郵便物を勝手に見ることは罪になる?
はい。家族であっても、他人の郵便物を本人の許可なく開ける行為は「信書開封罪」(刑法第133条)に該当するおそれがあります。信書開封罪とは、他人あての信書(手紙や通知など)を無断で開封した者に科せられる罪で、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が定められています。
「家族や同居人だから問題ない」と考える人も多いですが、法的には家族間であっても「他人の郵便物」とみなされます。特に離婚や別居中の元配偶者・子ども・親あての郵便を開封した場合は、トラブルにつながることも。
どうしても確認が必要な場合は、本人に連絡して了承を得るか、受取拒否や返送の手続きをとるのが安全です。
郵便の受け取り拒否には料金がかかりますか?
郵便の受け取り拒否には基本的に料金はかかりません。切手を貼る必要もなく、無料で差出人に返送できます。これは日本郵便が公式に認めている制度で、「受取拒絶」と書いたメモや付せんを封筒に貼り付け、署名・押印するだけでOKです。
ただし注意が必要なのは、民間配送サービス(ヤマト運輸・佐川急便など)を使って送られてきた荷物の場合です。これらは郵便法ではなく各社の利用規約で運営されており、返送に送料がかかることがあります。
もし着払いで返送になった場合、送料負担を避けるために、まず配送業者に「受け取り拒否をしたいが、返送料は発生するか?」を確認してから対応するのが安心です。
身に覚えのない郵便物の不在票が入っていた場合どうすればよいですか?
まずは不在票に記載された連絡先へ電話し、差出人情報を確認するのがおすすめです。不審な場合は「受け取り拒否したい」と伝えれば、対応策について案内してもらえるでしょう。しっかりと確認したうえで心当たりがないとわかった場合は、無理に再配達を依頼しないのが安全です。
受け取り拒否をしても郵便物が届いてしまう
受け取り辞退をしてもくりかえし郵便物が配達されるという場合、差出人に直接連絡をして受け取らない意思を伝えるなどの方法もあります。
それでも止まらない場合や、嫌がらせ目的で郵送されるケースでは、警察や弁護士への相談も視野に入れましょう。特に、架空請求やストーカー被害に関連する郵便は、法的な措置が必要なこともあります。
郵便局と連携して差出人調査を依頼できる場合もあるため、ひとりで抱え込まず、早めに専門機関へ相談するのがおすすめです。
「郵便物 受け取り拒否 家族」まとめ

家族あての郵便物であっても、原則として拒否できるのは「宛名の本人」のみです。勝手に返送するとトラブルの原因になるため、必ず本人の意思を確認してから手続きを進めましょう。
また、詐欺まがいの郵便物やしつこいDMの場合は、郵便物に「受取拒絶」と記載して返送することができます。
その他、誤配や不審な郵便が続くときは、無理に対応せず郵便局や警察に相談するのが安心です。
家族との暮らしで郵便物管理に困ったらMailMate

もし「自宅で郵便対応をしたくない」「家族に見られたくない郵便がある」と感じているなら、クラウド郵便受けサービスのMailMate(メールメイト)が便利です。
MailMateでは、あなた宛の郵便物を専用の私書箱で受け取り、内容をスキャンしてオンラインで確認できます。届いた郵便物の転送依頼もワンクリックで完了するため、わざわざ郵便局に行く必要もありません。
海外在住中や長期出張中でも郵便を安全に管理できるので、「家族に見られたくない郵便」や「受け取りたくないDM」がある人にもぴったりのサービスです。
クラウド郵便のMailMateなら架空請求・迷惑DMは開封前にフィルタリング。離婚後の元配偶者宛郵便も完全分離。高齢の親の郵便物も家族で共有して見守れます。
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

