テレワーク廃止の傾向が強まる理由!|企業がとるべき対策を紹介
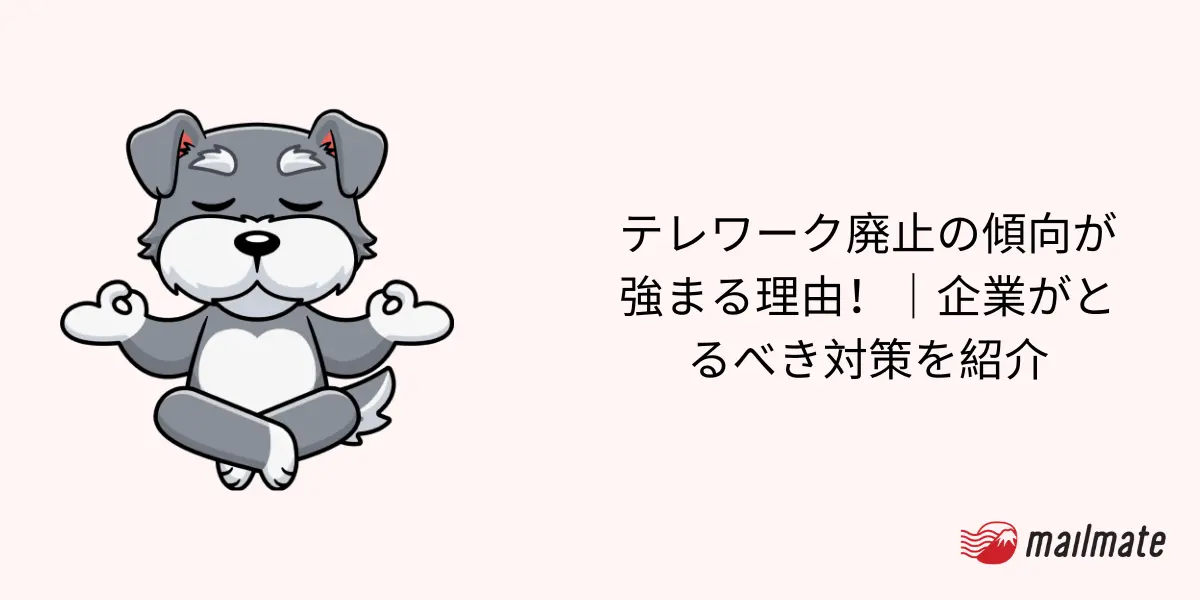
「企業がテレワーク廃止を進めているのはどうして?」
「オフィス勤務に戻すと生産性が下がりそう」
「時々聞くハイブリッドワークってどんなもの?」
この記事では、こうした疑問を解決していきます。
2020年頃、新型コロナウイルス感染症が流行し、日本でも働き方の変化が起こりテレワークが普及しました。ところが感染症の流行が落ち着いた昨今では、多くの企業でテレワークが廃止されています。
本記事では、企業がテレワークを廃止する理由やそのメリット・デメリット、これから企業がとるべき対策について解説します。テレワークを続けるかどうか悩んでいる方や、オフィス回帰の傾向に疑問を持っている方は、ぜひ参考にしてください。
クラウド郵便メールメイトで、会社宛の紙の郵便物をWEB上で確認・管理しませんか?郵便物の受領・確認のための出社、保管場所が不要になります。
なぜテレワークを廃止するのか?テレワークの抱える5つの課題

総務省の調査によると、テレワークの導入率は少しずつ上がり、2021年には過半数を超えて51.9%に達しました。ところが2022年には51.7%と微減し、2023年にはさらに49.9%まで下がっています。

引用:総務省|令和6年版 情報通信白書|テレワーク・オンライン会議
テレワーク廃止の理由として、感染症の流行が落ち着いたことを挙げる企業もあります。一方でテレワークの抱える課題を解決するために、廃止を決めた企業も多いです。
テレワークを廃止する企業が増えた理由、つまりテレワークの抱える課題は、主に5つあります。
1)従業員間でコミュニケーションが取りにくいため

テレワークの課題としてよく挙がるのが、社内コミュニケーションの減少です。
テレワーク中は従業員の間でコミュニケーションが取りにくく、こまめな情報共有が難しくなってしまいます。その結果、業務効率が悪くなるケースもあるでしょう。文字だけでやり取りしていると相手の表情が読めないため、誤解を招くことも多くあります。
なかには周りに相談しづらく抱え込んでしまう、孤独感に落ち込んでしまうなど、メンタル面での不調につながる方もいるほど。こうした問題を解決するために、オフィス回帰を求める企業が増えているのです。世界でも社内コミュニケーションの減少を理由に、テレワークを廃止する企業は多いですよ。
2)従業員の帰属意識が低下するため
帰属意識が高い状態とは、「自分はこの組織に属している」という自覚があり、組織に対して愛着を抱いている状態。仕事のモチベーションが高まり、他のメンバーと協力しながら一体感のある仕事ができる状態です。帰属意識が高い企業は、従業員の定着率も高い傾向にあります。
ただ、テレワーク中は従業員がバラバラに仕事をしているため、帰属意識が低くなりがちです。するとモチベーションの低下や人材定着率の低下、さらに業務効率の悪化にもつながりかねません。だからこそオフィス勤務に戻すことで、帰属意識を高めようとする動きがあるのです。
3)人事評価や労務管理が難しいため
テレワーク中は、上司が部下の仕事の様子を細かく見ることはできません。そのため成果を数値化しづらい業種では、人事評価が難しいという課題があります。
また労務管理の難しさも課題です。オフィス勤務時と同じ方法では管理ができないため、新たなツールや手順を導入する企業も多いでしょう。それによって業務量の増加、作業効率の低下を招いたケースもあります。
4)生産性が下がるケースも多いため

テレワークを導入することで生産性が高まる場合はあるものの、実際には「在宅勤務のほうが生産性は低い」と感じる従業員・企業が圧倒的多数となっています。
引用:コロナ禍の経済への影響に関する基礎データ(内閣官房・経済産業省)
生産性が低くなる理由としては、主に以下が挙げられます。
対面での情報交換ができない
パソコンやインターネット回線などの設備環境がよくない
自宅ではできない業務がある
自宅でできない業務には、たとえば郵便物の仕分けや書類への押印があります。こうした業務のためにテレワーク中の出社が義務付けられる部署もあり、生産性が落ちてしまうのです。
また人によってITスキルに差があるために、生産性にバラつきが出ることも考えられます。
5)セキュリティリスクが高まるため
自宅やカフェなどで仕事をする場合、会社と比べてセキュリティ体制が整っていないことが多いです。そのためサイバー攻撃やウイルス感染の影響を受けやすく、情報漏洩などのトラブルを招く恐れがあります。
さらにカフェなど不特定多数が集まる場で仕事をしていると、気付かずに情報を漏らしてしまうリスクも高まります。特に離席中にパソコン画面を見られる、あるいは電話の声を聞かれるという事例が多いので、トラブル防止のためにも対策を練っておく必要があるでしょう。
テレワーク廃止のメリット

テレワークを廃止すれば、当然テレワークの課題は解消されます。そのため以下のメリットが得られます。
従業員間のコミュニケーションがとりやすくなる
会社への帰属意識が高まる
労務管理や人事評価がしやすくなる
生産性向上が見込める
セキュリティリスクが下がる
ただ、単にテレワークを廃止するだけでは、柔軟な働き方を難しくしてしまいます。テレワークの廃止を決める前に、廃止することのデメリットも確認しておきましょう。
テレワーク廃止のデメリット

企業規模が大きいほどテレワークの実施率も高く、大手企業のなかには感染症が流行する前から実施しているところもあります。
実際にテレワークを行った企業や従業員は、以下の効果を感じています。
企業:働き方改革が進んだ、業務プロセスの見直しができた など
従業員:通勤時間を有効活用できる、オフィスにいるより集中できる など

引用:令和5年度 テレワーク人口実態調査-調査結果(概要)|国土交通省
テレワークを廃止すればこうした効果がなくなるのはもちろん、ほかにも数々のデメリットが生じます。
1)従業員のワークライフバランスが悪化する
テレワークの大きなメリットに、通勤時間がかからないことが挙げられます。その分空いた時間を自分や家族に時間を使えるため、ワークライフバランスが向上するのです。
反対にテレワークを廃止すれば、家で過ごす時間が大きく減るため、ワークライフバランスが悪化すると考えられます。
2)人材流出のリスクが高まる
テレワークを廃止し、ワークライフバランスが崩れると、従業員の満足度低下を招く可能性があります。その結果、退職者や転職者が増えてしまうかもしれません。
さらに近年では、柔軟な働き方を求める人が増加。テレワークの有無が会社を選ぶ際のポイントという人も多いです。つまりテレワークを廃止することで、人材が流出するだけでなく、新しい人材が入りにくくなる可能性もあります。
3)オフィスにかかるコストが増大する
テレワークを廃止し、原則出社の方針に切り替えると、オフィスコストが増大します。具体的には、以下のコストが増えるでしょう。
消耗品費(ボールペン、コピー用紙、ホッチキス など)
水道光熱費、通信費
交通費
場合によっては備品の再購入もしなければなりませんし、オフィスの拡張や移動が必要であればその費用もかかります。
4)BCP対策が進みにくくなる
BCP対策とは「Business Continuity Plan」、つまり事業継続計画のこと。コロナ禍のように感染症が流行した場合や、自然災害が起きた場合、テロやサイバー攻撃を受けた場合などに、どのように事業を継続するのか計画しておくことを指します。
BCP対策として有効な手段の一つが、テレワークです。テレワークがあれば交通機関が停止しても業務を続けられますし、感染症の拡大も防げるでしょう。
そのためテレワークを廃止した場合、それに代わるBCP対策を考えなければなりません。
テレワークを廃止した企業一覧

ここではテレワークの廃止や縮小を決めた日本企業、海外企業のなかから、代表的なところをまとめてご紹介します。
Amazon:週5日出社を義務化
Apple:週3日出社を義務化
GMO:原則出社の方針に転換
Google:週3日出社を義務化
Zoom:最低週2日出社を義務化
テスラ:最低週40時間の出社を義務化
ホンダ:原則出社の方針に転換
楽天:原則週4日出社の方針に転換
このほかサントリーや日清食品も、出社推奨の方針に切り替えています。
またAmazonやテスラのように実質テレワークを廃止しているところもあれば、出社を推奨しつつテレワークも認めているところもあるように、企業によって対応に差があります。
【テレワークを継続する?廃止する?】企業に求められている対応とは

そもそもテレワーク実施率は、業種によって大きく異なります。

引用:令和5年度 テレワーク人口実態調査-調査結果(概要)|国土交通省
たとえば以下は実施率が高く、テレワークに向いている業種といえます。
情報通信業
学術研究、専門・技術サービス業
金融・保険業
こうした業種はテレワークによって成果が出やすく、うまく導入すれば生産性の向上が見込めます。
一方、以下の業種はテレワークに不向きといえるでしょう。
宿泊業・飲食業
医療、福祉
生活関連サービス業
対人サービスはリモート対応が難しく、テレワークで成果を出しにくい業種です。無理にテレワークを進めても、生産性は上がらない可能性があります。
テレワークを続けるか否か悩んだ時は、「業種に合った働き方か」という視点で考えてみましょう。
テレワークに向かない企業は廃止を検討するのもあり
テレワークの向き・不向きは業種だけでなく、企業ごとにも異なります。そのため一概に「継続すべき」「廃止すべき」とはいえません。ただしテレワークに向いていない企業には、以下のような特徴があります。
社内のコミュニケーションが不足している
セキュリティ体制が甘い
自宅のテレワーク環境が整えられていない
書類を紙ベースで管理しておりハンコ文化が残っている
このような企業は、テレワークによって生産性が低下する可能性があります。場合によっては情報漏洩などのトラブルを招くかもしれません。
まずはこうした課題の解決を目指し、解決が難しい場合にテレワーク廃止を検討するとよいでしょう。
テレワークを完全廃止する前にハイブリッドワークを検討しよう
突然テレワークを廃止すると、従業員の不満を招き、離職率の増加につながります。あらかじめ従業員にアンケートを渡し、意見や希望を聞くなど工夫しましょう。
またテレワークには「継続する」「廃止する」だけでなく、「一部継続する」という選択肢もあります。それがテレワークとオフィスワークを組み合わせた、ハイブリッドワークという働き方です。
ハイブリッドワークのメリット
ハイブリッドワークの導入は、テレワークによるコミュニケーション不足の解決策として有効です。完全なオフィス勤務と比べて、従業員のワークライフバランスや満足度を高く保てるのもメリットといえます。
週に数回のテレワークを行うことで、オフィスコストを下げられるのもポイントです。
ハイブリッドワークのデメリット
ハイブリッドワークを導入すると、オフィス勤務やフルリモートワークよりも労務管理が難しくなってしまいます。またどの社員がどこにいるのか把握していないと、スピーディーな報告・連絡・相談がしづらい点もデメリットです。
そして週に数回でもテレワークを行う以上、セキュリティリスクも残り続けます。従業員にセキュリティ教育を行うなど、対策しなければなりません。
クラウド郵便メールメイトで、会社宛の紙の郵便物をWEB上で確認・管理しませんか?郵便物の受領・確認のための出社、保管場所が不要になります。
テレワークの課題を解決するシステム3選
テレワークにはいくつか課題がありますが、なかにはシステム導入によって解決できるものもあります。フルリモートワークを継続する企業も、ハイブリッドワークに切り替える企業も、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
①郵便物の課題を解決する「クラウド郵便サービス」

テレワーク中にもかかわらず郵便物のために出社するのは、効率が悪いうえに担当者とそれ以外の方で不平等感が生まれてしまいます。そんな課題を解決するのが、メールメイトをはじめとするクラウド郵便サービスです。
クラウド郵便サービスを使えば、会社宛の郵便物がデータ化され、クラウド上で管理できるようになります。わざわざ出社しなくても、パソコン上で郵便物の受け取りや確認ができるため、テレワークの生産性を下げることがありません。データなので簡単に共有できますし、保管や検索も容易です。
またメールメイトの場合は、郵便物が届くとSlackやメールで通知が来ます。そのため郵便物を見逃すことなく、スムーズに対応できますよ。
クラウド郵便 MailMateで、複数の拠点に届く紙の郵便物をパソコン・スマホ上のダッシュボードで一括確認・管理できます💻📩 郵便物のスマート管理始めませんか?
②社内のコミュニケーションを促進する「チャットツール」

引用:Slack
従業員のコミュニケーション不足を解消するには、SlackやChatworkなどのチャットツールを導入するのがおすすめです。スピード感のあるやり取りができ、報告・連絡・相談もしやすいこともあり、Slackユーザーの90%が「Slackでつながりが強くなった」と回答しています。
プロジェクトごと、チームごとなど少人数のグループを作れば、より気軽なメッセージが送りやすいです。さまざまなリアクション機能が付いており、反応を返しやすいのも便利なポイント。テキストメッセージの送受信だけでなく、ファイルの共有やタスク管理にも使えるため、生産性も高まるでしょう。
③労務管理がスムーズになる「勤怠管理システム」

引用:キンコン
勤怠管理システムを使えば、テレワーク中の労務管理を効率よく行うことができます。キンコンやジョブカン、楽楽勤怠などシステムの種類も豊富です。
勤怠管理システムには、たとえば以下のような機能があります。
出退勤時間の打刻
アラート(未打刻、残業時間の超過など)
休日・休暇の申請
シフト管理
テレワーク対応のシステムなら、Web打刻やアプリ打刻ができるため、自宅からでも出退勤の記録が可能。複数の打刻方法があるシステムを選べば、毎日の働き方が異なる場合も対応しやすいです。
大きく「勤怠管理特化型」「人事労務型」に分けられるため、企業に合ったタイプを選びましょう。
テレワーク廃止に関するよくある質問

最後によくある質問をご紹介していきます。
なぜ最近テレワークを廃止する企業が増えているのですか?
主な理由として、社内コミュニケーションの減少や従業員の帰属意識の低下、人事評価や労務管理の難しさ、生産性の低下、セキュリティリスクの増大などが挙げられます。企業はこれらの課題を解消し、業務効率やチームの一体感を取り戻すためにオフィス勤務へ回帰する傾向があります。
テレワークを完全に廃止する以外に、企業がとれる柔軟な選択肢はありますか?
テレワークと出社勤務を組み合わせた「ハイブリッドワーク」が注目されています。これは柔軟な働き方を維持しつつ、コミュニケーション不足や生産性のバラつきといった課題に対応できるため、従業員の満足度を保ちながら業務効率を高める手段として、多くの企業で導入が進んでいます。
テレワークの課題を解決して仕事環境を整えよう

テレワークはコロナ禍に広く普及しましたが、近年ではその状況が変化しています。テレワークにはコミュニケーションの難しさや生産性の低下、セキュリティリスクなどの課題が多く、オフィス回帰を進める企業が増えているのです。
ただテレワークを廃止すると、ワークライフバランスの悪化や人材流出リスクなどのデメリットも生じます。そのためハイブリッドワークを導入する企業も増えています。
またテレワークの課題を解決するには、システムの導入も効果的です。たとえばメールメイトを使うと郵便物の管理がしやすくなり、テレワーク環境を改善できますよ。企業に合ったシステムを活用しながら、仕事環境を整えていきましょう。
クラウド郵便MailMateが、会社の郵便物の受け取り代行・スキャン・PDF化・管理画面へ配信いたします。利用開始から30日間は全額返金保証付き 🎉
おすすめ記事:
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

